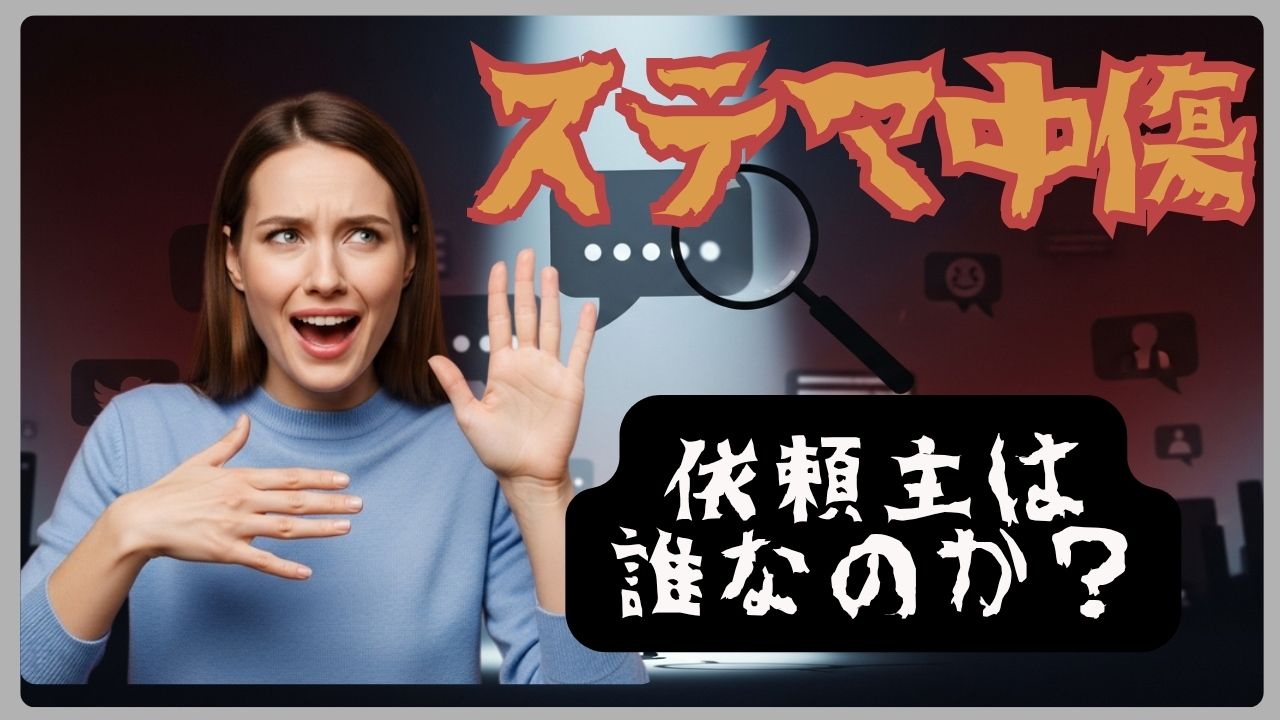わかりやすく株式会社ダイアログ松田馨代表が声明を発表
総裁選でのステマがバレた小泉進次郎。
主犯は牧島かれんと思われるも、受注会社の社長が自社だと発表。
国民を騙すためのコメント、高市早苗をエセ保守などと誹謗中傷するコメント。
作った人はわかった。
問題はこの仕事を画策した人間と、実際に発注した人間。
誹謗中傷を行っておきながら、被害を受けているとはギャグなのか・・・
まぁでもこれでまた、真実に気づく日本人が増えることになる。
過ぎたことをぶり返し、ツッコミどころを作り継続させる。
これってむしろ多くの国民に気づかせるためのイベント?と疑ってしまいます。
今までだったら隠しもできるしスルーもできる。
しかしあえて何度も、反論の余地のない悪事を追及する不思議。
売国左翼である、小泉進次郎側の悪事を徹底的に暴くのが目的なのか?
だとしても、なぜ隠せなくなったのか???
何らかの正義の勢力が働いている、なんて陰謀論だったはずですよね?
🧭 ステマに誹謗中傷を指示したのは?
自民党の牧島かれん元デジタル大臣
状況と文脈的に、小泉進次郎のステマを画策したのは、牧島かれんと考えるのが妥当。
ダイアログ松田馨代表によると、牧島氏がコメント例を作成しその投稿を主導したのではない。
ただこの声明では、コメント例を作成したのは自社である。
残る問題は、投稿を主導したのは誰なのか? 依頼そのものを発注したのは誰か?
このもっとも大切な問題には解答できない事情があるのでしょう。
❌ ステルスマーケティングの本質的な問題
- 透明性の欠如:選挙活動において、支援者によるコメント投稿を「自然な応援」と見せかけながら、実際には陣営側が文例を作成・指示していたことは、情報操作に近い行為であり、民主主義の根幹を揺るがす。
- 有権者の信頼を裏切る行為:政治家の発言や支持の流れが「演出されたもの」であると判明した場合、有権者は正当な判断を下す機会を奪われる。これは選挙の公平性を損なう重大な倫理違反である。
⚖️ 法的観点からの懸念
- 現時点で明確な違法性が確定しているわけではないが、公職選挙法に抵触する可能性が指摘されている。特に、報酬の有無や投稿の指示内容によっては「選挙運動の買収」や「虚偽表示」に該当する恐れがある 日刊スポーツ Note スポーツ報知。
🧨 倫理的責任の所在
- 牧島かれん氏の責任回避姿勢:声明では「従業員が作成した」として責任の所在を曖昧にしているが、広報班長としての監督責任は免れない。政治家としての説明責任と誠実さが問われる。
- 株式会社ダイアログの対応の不誠実さ:謝罪と抗弁が混在した声明は、危機管理としても不適切。報道後の「火消し対応」は、問題の本質を軽視していると受け取られかねない Note。
🧱 民主主義への影響
- このような情報操作的手法は、民主主義の健全なプロセスを損なう。選挙は国民の意思を反映する場であり、裏工作によってその意思が歪められることは、制度そのものへの不信感を助長する。
🕰️ ステマ問題:時系列
📌 2024年9月頃(推定)
- 自民党総裁選に向けて、小泉進次郎農相が立候補を表明。
- 牧島かれん氏が小泉陣営の「総務・広報班長」に就任。
📌 2024年9月〜10月
- SNS上で、小泉氏を支持する一般人風の投稿が多数出現。
- 実際には、選挙プランナー松田馨氏が代表を務める「株式会社ダイアログ」が、投稿文例を作成し、支援者に配布していたことが判明。
📌 2025年10月初旬
- 一部メディアが「ステルスマーケティング疑惑」として報道。
- 投稿文例の存在や、組織的な情報操作の可能性が指摘される。
📌 2025年10月10日頃
- 株式会社ダイアログの松田馨代表が声明を発表。
- 「従業員が独断で作成した」と説明。
- 「牧島氏は関与していない」と主張。
- 一方で、投稿文例の存在は認め、謝罪の意を表明。
📌 2025年10月中旬
- 牧島かれん氏は公式な謝罪や説明を行っていない。
- SNS上では「説明責任を果たすべき」「選挙活動の透明性が損なわれた」と批判が拡大。
- 一部識者や政治評論家が「公職選挙法違反の可能性」や「民主主義への脅威」として問題視。
🗳️ ステマ問題と政治倫理に関するFAQ
🧭 ステルスマーケティングとは何ですか?
ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であることを隠して宣伝行為を行う手法です。
背景には、企業や政治団体が「自然な支持」や「一般人の声」を装って情報を拡散する意図があります。
この手法は消費者や有権者の判断を誤らせるため、倫理的に問題があり、選挙活動では特に透明性が求められます。
⚖️ 今回のステマ問題は違法なのですか?
現時点では違法性が確定していませんが、公職選挙法違反の可能性があります。
背景として、報酬の有無や投稿指示の内容によっては「買収」や「虚偽表示」に該当する恐れがあります。
違法でなくとも、選挙の公平性を損なう行為は政治倫理上重大な問題です。
🧨 牧島かれん氏はステマに関与していたのですか?
公式声明では「従業員が独断で作成した」とされ、牧島氏の直接関与は否定されています。
ただし、広報班長としての監督責任があるため、倫理的な責任は免れません。
説明責任を果たさない姿勢は、有権者の信頼を損なう要因となります。
📣 SNSでの応援コメントはステマになるのですか?
応援コメント自体は通常の選挙活動の一環として認められています。
しかし、投稿文例を配布し、組織的に誘導する場合は「自然な支持」とは言えず、ステマと見なされる可能性があります。
特に報酬が発生する場合は、広告表示義務が生じるため注意が必要です。
🧱 この事件は民主主義にどんな影響を与えますか?
情報操作による選挙活動は、民主主義の健全なプロセスを損ないます。
背景には、有権者の判断材料が「演出された情報」によって歪められる危険性があります。
結果として、政治への不信感が高まり、制度そのものの信頼性が揺らぐ可能性があります。
🕵️♂️ 株式会社ダイアログの責任はどうなりますか?
ダイアログ社はコメント文例の作成を認め、謝罪を表明しています。
背景には、社内のガイドライン不足やチェック体制の不備がありました。
今後は再発防止策として、複数チェック体制や役員報酬の減額などを実施するとしています。
🤔 なぜ「ステマ」と報道されたのですか?
報道では、投稿文例の配布や組織的な誘導が「広告的性質を持つ」と判断されたためです。
背景には、視聴者に「自然な支持」と誤認させる構造がありました。
このような手法は、報酬の有無にかかわらず、ステマと見なされるリスクがあります。
🧮 どのような条件でステマは違法になりますか?
ステマが違法となる条件は、主に以下の通りです:
- 報酬を受け取っているにもかかわらず広告表示をしていない
- 虚偽の情報を意図的に拡散している
- 公職選挙法に抵触する選挙運動と認定される
これらは、選挙管理委員会や司法判断によって判断されます。
📅 この事件はいつ起きたのですか?
事件の発端は2024年9月頃、小泉進次郎氏の総裁選立候補に伴う広報活動です。
2025年10月初旬に報道が出て、10月10日頃にダイアログ社が声明を発表しました。
その後、SNSやメディアで批判が拡大し、政治倫理が問われる事態となりました。
😠 なぜ誰も責任を取らないのですか?
現時点では、関係者は「誤解」「独断」「不備」といった表現で責任を回避しています。
背景には、法的責任の回避や政治的ダメージの最小化があると考えられます。
しかし、説明責任を果たさない姿勢は、信頼回復を困難にし、政治不信を助長します。
🔗 参考リンク:
「コメント例文は当社の従業員が作成」
小泉進次郎氏陣営「ステマ問題」選挙プランナーが声明「コメント例文は当社の従業員が作成」
https://news.yahoo.co.jp/articles/b9553219ead1a852fd9650234cdd9aa766abbac3自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相(44)の陣営で総務・広報班長を務めた自民党の牧島かれん元デジタル相の「ステマ問題」について、選挙プランナーで株式会社ダイアログ松田馨代表が声明を発表した。
松田氏は同社公式サイトに「自民党総裁選に関する週刊誌報道について」との声明文を掲載。牧島氏の事務所関係者が、動画サイト「ニコニコ動画」で、進次郎氏に好意的なコメントを投稿するよう、文例などを作成して依頼していたとの報道について「これにより牧島氏の名誉が毀損され、誤解が広がっていることに対し、当社として正確な情報を発信すべきと判断し、コメントを発表します」と説明した上で、「各種報道を受けて社内調査を行ったところ、当該コメントの例文案を作成したのは、当社の従業員であることを確認いたしました。したがいまして今回の総裁選の動画配信に関し、牧島氏がコメント例を作成しその投稿を主導したかのように受け取れる記事の記載は、事実と異なります」とした。
続けて「政治家がニコニコ動画への出演にあたり、支援者に対して応援コメントを呼びかけること自体は、通常の選挙運動においても広く行われているものです」と説明し、「報酬を受け取る広告であることを隠した『ステマ』に該当するものではなく、これを『ステマ』と報道することは、誤った印象を与えかねないものであると言わざるをえません」と指摘するとともに、「ただ当社は、我が国のために働こうとする政治家の皆さまに対する尊敬に基づき、その志を支えることを使命としてきました。